子どもの貧困問題を考える
NPO法人Learning for All代表理事の李炯植(り・ひょんしぎ)氏とゴールドマン・サックス証券持田昌典元社長(現シニアアドバイザー)が、子どもの貧困問題について意見を交わしました。
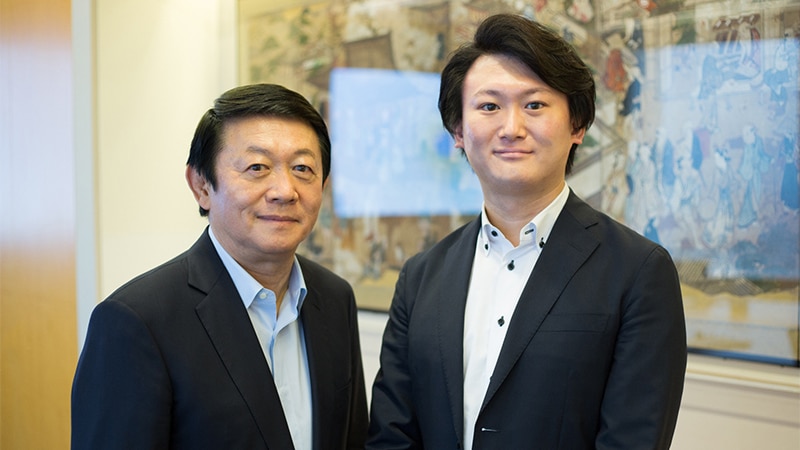
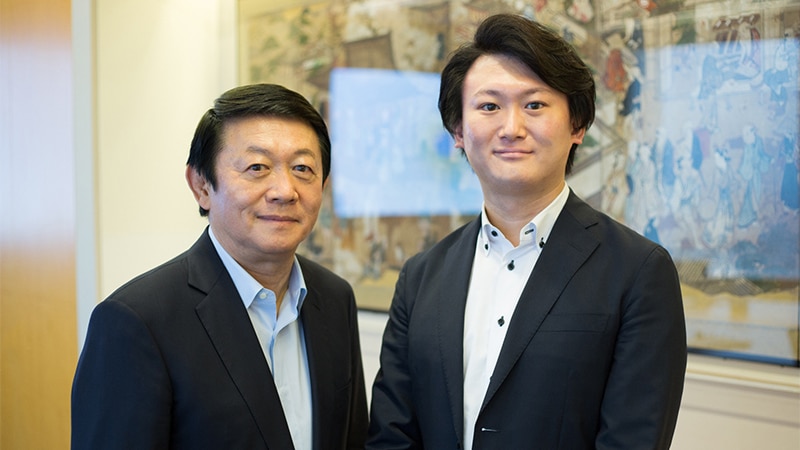
支援も確かに拡充されましたが、行政の連携が取れないことが根本的なハードルとしてあります。現場の声が政策を作る政府に直接届いていないので、年齢層の高い政治家の多くは自己責任論で教育観を展開し、効果的な政策をつくれないでいます。子どもの貧困問題への政策でも同様に、意欲がある、勉強したいと思っている子どもには手を差し伸べるが、意欲がなく、自分から落ちこぼれていくような人たちへの支援は消極的です。しかし背景を理解していくと、例えば虐待されている子どもたちは頑張る意欲さえ奪われているのに、意欲があるかないかだけで測られてしまうと子どもの貧困問題を解決するにあたって大きなハードルとなります。
持田:子どもは国の宝であるにもかかわらず、今も貧困の中で暮らす子どもがたくさんいる。政府の対策も万全ではない中で頑張っている李さんにはこれからも協力していきたいです。
李:持田さんが常日頃からおっしゃっているように、貧困の子どもたちを支えることは社会への投資であって、必ず将来リターンが返ってくるわけですし、生活保護を受けている人が増えれば社会保障制度、国の財政が圧迫されていきますが、日本の政策においてはここに関するエビデンスは全体的に少ない印象です。データをもとに議論を展開すれば、意思決定の仕方自体を改善できると思います。
持田:そうですね、子どもの貧困問題というのは社会全体にとって極めて重大な問題なのに、人々の当事者意識は相対的にとても低いと感じます。こんな問題あったんですか?と思っている人もいると思います。その一方で、例えばですが児童福祉法が改正したので、里親制度などの普及は進んでいると思います。私なんかは個人的にたくさんの子どもの里親になりたいと思っていますが、それは根本的なソリューションにはなりません。里親制度の認知度がもっと広がり、制度を利用しやすい世の中になっていったらいいと思いますし、人々の理解を深められる取り組みがあるのならば協力していきたいです。
子どもの貧困問題に取り組むうえでの李さんのモチベーションはなんですか?
李:私は21歳の時からこの問題に携わっていますが、数年前までは自分が貧困の地域に生まれ育ったという実体験をベースに過去と戦っていた気がします。でも情熱だけではすぐに燃え尽きてしまいました。そんな中で、持田さんをはじめいろんな人に支えてもらっていることに気づき、たくさんの子どもたちと出会い、支援の輪がどんどん広がっていきました。LFAが大きくなり、よりたくさんの子どもをサポートできることが今の最大のモチベーションです。
持田:ある意味、事業と一緒ですね。自分が一生懸命時間と能力を注ぎ込んできたものが人の役に立ったり、認められたり、一つのパワーになってくるとやりがいがありますよね。このような社会問題に対してこれだけのやりがいを見出せて、取り組めるということは大変素晴らしいと思います。
李:ありがとうございます。地域でサポートしてきた小学生たちが成長して大学生になるのを見ると本当にうれしいです。サポートしてきた子の一人に、生活保護を受けて塾にも行けなかった子がいるんですが、海外で活躍したいから英語を勉強できる大学に進学して留学するつもりだと聞いた時には、この活動をやっていて本当に良かったと思いました。
持田:私も児童養護施設の子どもたちの進学相談にのってきましたが、こうした1対1の関係を通じて子どもたちを近くで見れば見るほど、この問題の大変さを知りました。たくさんの子どもがうまくいくわけでないことも知っています。本当にこの問題は複雑ですね。
李:期待をかけてもらえるかどうかで子どもの成長、サクセスは大きく変わっていきます。「夢を叶えるために努力すればサポートするよ」と言ってもらえる環境がない子どもがいっぱいいます。
持田:期待という外部からの働きかけと、諦めないで最後までやり切る力を持っている子どもは、困難な環境にいても成長すると思います。だから早い段階から期待をかけてあげ、そしてグリットを育てていければいいですよね。
李:今までたくさんの子どもを見てきましたが、6歳ですでに人格構成はできていて、なんでもすぐに諦めてしまう子どももいます。そんな子どもにはこちらの方が諦めずに何度も何度もこうしよう、ああしようと取り組んで、育てていきます。
持田:そうですね、根気よく子どもを育てていくのは、社員を根気よく育てていくという点で同じだと思います。それから、社員一人一人がいろいろな社会問題を知り、地域に貢献していけるように教育するのも会社の重要な使命の一つだと思っています。社会の一員として、私たちは今後どのように子どもの貧困問題に取り組むべきだと思いますか?
李:貢献の仕方はそれぞれですが、住んでいる地域の子どもの居場所拠点、子ども食堂に参加するなどして、それをきっかけに身の回りに子どもの貧困が存在するということを知ってもらいたいです。自分の周りにはいないと思っていても、子どもの貧困はどの地域でも必ず存在します。そのような子供と知り合い、社会を共につくっていってもらいたいです。そうしないとこの国は10年後本当に取り返しのつかないことになってしまいます。これまで貧困を放置してきた社会で、成功してきた社会はないと思います。待ったなしで今やっていただきたい。
持田: 個人も企業も自分ごととして捉えて、そこにあるものなのだと実感して体感して、協力してほしいということですね。
私ではあまり力になれないかもしれませんが、李さんの志を支え、助けになれればと思っています。CESも徐々に日本全国に浸透して、例えば私と李さんの1対1の会話が、もっと大勢での議論になって、世の中を変えるような動きになってほしいと思っています。子どもの貧困問題の解決は李さん一人、LFAという一つの団体だけでは解決できませんよね。だからこそCESのコンセプトに賛同してくれる全国の協力団体と一緒に、地域に根ざした形でたくさんの子どもたちを救っていく、それがどんどん広がっていったらうれしいです。コロナが明けたら、各地を一緒に周って視察し、その後に同じ志を持った地域の人たちと美味しいお酒を分かち合えたら最高だと思います。全国ネットに広げていけるように着実に前に進んでほしいです。そのためのサポート、支援をこれからも行っていきたいです。
持田:李さんと初めてお会いしたのは確か2017年でしたね。子どもの貧困解決に取り組む団体を新たに支援したいと思っていたところ、LFAを紹介されました。子どもの貧困という課題解決の手法として、モデルを作って全国展開するいう斬新なアイデアに興味を持ちました。
李:ゴールドマン・サックスさんに支援していただき、2018年から困難を抱えた子どもたちへの包括的支援モデル(CES)の構築に取り組んでいます。このモデルでは包括的に子どもをサポートできるように、まずは地域とつながり、早期に困難を抱える子どもを見つけて必要な支援につなげ、適切な支援を切れ目なく提供していきます。現在では関東地域に複数の子どもの居場所拠点を運営したり、学校にLFAスタッフを派遣して学習支援を行ったりしており、2020年までの3年間で延べ1,724人の子どもたちとつながることができました。子どもの貧困は潜在的で、子ども自身自ら助けを求めるのが難しいからこそ、地域や学校・行政など様々なステークホルダーと連携し、支援を必要とする子どもを見つけ出し、手を差し伸べることが CESモデルを通じてできるようになってきました。
持田:LFAがテーマとしている「見つける、つなげる、支える」では、やはり「見つける」の部分が一番大変なのでしょうか?
李:そうですね。困難な状況にいる子どもであればあるほど、見つけて支援につなげることが難しいです。それには行政や学校、地域、NPO、マルチステークホルダーの連携が必要不可欠ですが、うまく連携できている地域はほとんどなくて、そこがこの3年で一番苦しかったところです。でもうまく連携できるようになってからは本当にたくさんのしんどい子どもたちとつながることができたと思います。
持田:様々なステークホルダーの中でも、この問題をよく理解しているのはどういった方々だと思いますか?
李:これは非常に難しい質問ですね、私は本当に「人」によると思っています。学校の先生でも非常に高い意識を持っている人もいれば、持っていない人もいます。なのでLFAは、新しい地域やコミュニティに入っていくときには必ず最初に「人」を見て、各地域のキーマンは誰かと考えて、そこから切り崩していきます。問題意識がないのではなく、そもそもの貧困問題という課題があることを知らない人があまりにも多い。知ってもらうところからスタートしないといけません。
持田:支援企業はどれぐらいに増えましたか?
李:おかげさまでこれまで40社近い企業から支援をしていただいています。近年ではSDGsの観点からご寄付いただけることも増えていると思います。どの企業様もLFAの取り組みに共感していただいています。中でも持田社長は、貧困に置かれた子どもたち一人一人に共感し、課題にコミットし、問題を解決しないといけないという当事者意識を持って取り組んでくださっていることには本当に感謝しています。
持田:そう言っていただけると私もとてもうれしいですね。現場に足を運んで実際に子どもたちと触れ合うことで支援の意義や共感が湧くと思っています。
私も15年ほど前から困難な子どもの支援をしてきましたが、そうそう簡単に子どもの貧困はなくならない。なかなか状況は変わらないと思っていましたが、李さんのように若くて、トータルソリューションとして子どもの貧困問題を考えられる人が出てきたことは大きな変化だと思います。自分の考えたソリューションモデルをある地域で実践し、その有効性を検証し、そして徐々に行政を巻き込みながら地域を拡大していく。そういったやり方は15年前にはあまり見られなかったと思います。
李さんから見て子どもの貧困課題への対応にはどういう進歩があったと思いますか?
李:大学時代にボランティアを始めてから今までを振り返ると、子どもの貧困対策法、生活困窮者自立支援法などが施行され、日本における貧困問題が明らかになってきたのがこれまでの15年だと思います。90年代はこの問題に目を向ける人はいませんでしたが、2000年以降生活保護率が上がったり、2008年には子どもの貧困という言葉が出てきて注目されるようになりました。
支援も確かに拡充されましたが、行政の連携が取れないことが根本的なハードルとしてあります。現場の声が政策を作る政府に直接届いていないので、年齢層の高い政治家の多くは自己責任論で教育観を展開し、効果的な政策をつくれないでいます。子どもの貧困問題への政策でも同様に、意欲がある、勉強したいと思っている子どもには手を差し伸べるが、意欲がなく、自分から落ちこぼれていくような人たちへの支援は消極的です。しかし背景を理解していくと、例えば虐待されている子どもたちは頑張る意欲さえ奪われているのに、意欲があるかないかだけで測られてしまうと子どもの貧困問題を解決するにあたって大きなハードルとなります。
持田:子どもは国の宝であるにもかかわらず、今も貧困の中で暮らす子どもがたくさんいる。政府の対策も万全ではない中で頑張っている李さんにはこれからも協力していきたいです。
李:持田さんが常日頃からおっしゃっているように、貧困の子どもたちを支えることは社会への投資であって、必ず将来リターンが返ってくるわけですし、生活保護を受けている人が増えれば社会保障制度、国の財政が圧迫されていきますが、日本の政策においてはここに関するエビデンスは全体的に少ない印象です。データをもとに議論を展開すれば、意思決定の仕方自体を改善できると思います。
持田:そうですね、子どもの貧困問題というのは社会全体にとって極めて重大な問題なのに、人々の当事者意識は相対的にとても低いと感じます。こんな問題あったんですか?と思っている人もいると思います。その一方で、例えばですが児童福祉法が改正したので、里親制度などの普及は進んでいると思います。私なんかは個人的にたくさんの子どもの里親になりたいと思っていますが、それは根本的なソリューションにはなりません。里親制度の認知度がもっと広がり、制度を利用しやすい世の中になっていったらいいと思いますし、人々の理解を深められる取り組みがあるのならば協力していきたいです。
子どもの貧困問題に取り組むうえでの李さんのモチベーションはなんですか?
李:私は21歳の時からこの問題に携わっていますが、数年前までは自分が貧困の地域に生まれ育ったという実体験をベースに過去と戦っていた気がします。でも情熱だけではすぐに燃え尽きてしまいました。そんな中で、持田さんをはじめいろんな人に支えてもらっていることに気づき、たくさんの子どもたちと出会い、支援の輪がどんどん広がっていきました。LFAが大きくなり、よりたくさんの子どもをサポートできることが今の最大のモチベーションです。
持田:ある意味、事業と一緒ですね。自分が一生懸命時間と能力を注ぎ込んできたものが人の役に立ったり、認められたり、一つのパワーになってくるとやりがいがありますよね。このような社会問題に対してこれだけのやりがいを見出せて、取り組めるということは大変素晴らしいと思います。
李:ありがとうございます。地域でサポートしてきた小学生たちが成長して大学生になるのを見ると本当にうれしいです。サポートしてきた子の一人に、生活保護を受けて塾にも行けなかった子がいるんですが、海外で活躍したいから英語を勉強できる大学に進学して留学するつもりだと聞いた時には、この活動をやっていて本当に良かったと思いました。
持田:私も児童養護施設の子どもたちの進学相談にのってきましたが、こうした1対1の関係を通じて子どもたちを近くで見れば見るほど、この問題の大変さを知りました。たくさんの子どもがうまくいくわけでないことも知っています。本当にこの問題は複雑ですね。
李:期待をかけてもらえるかどうかで子どもの成長、サクセスは大きく変わっていきます。「夢を叶えるために努力すればサポートするよ」と言ってもらえる環境がない子どもがいっぱいいます。
持田:期待という外部からの働きかけと、諦めないで最後までやり切る力を持っている子どもは、困難な環境にいても成長すると思います。だから早い段階から期待をかけてあげ、そしてグリットを育てていければいいですよね。
李:今までたくさんの子どもを見てきましたが、6歳ですでに人格構成はできていて、なんでもすぐに諦めてしまう子どももいます。そんな子どもにはこちらの方が諦めずに何度も何度もこうしよう、ああしようと取り組んで、育てていきます。
持田:そうですね、根気よく子どもを育てていくのは、社員を根気よく育てていくという点で同じだと思います。それから、社員一人一人がいろいろな社会問題を知り、地域に貢献していけるように教育するのも会社の重要な使命の一つだと思っています。社会の一員として、私たちは今後どのように子どもの貧困問題に取り組むべきだと思いますか?
李:貢献の仕方はそれぞれですが、住んでいる地域の子どもの居場所拠点、子ども食堂に参加するなどして、それをきっかけに身の回りに子どもの貧困が存在するということを知ってもらいたいです。自分の周りにはいないと思っていても、子どもの貧困はどの地域でも必ず存在します。そのような子供と知り合い、社会を共につくっていってもらいたいです。そうしないとこの国は10年後本当に取り返しのつかないことになってしまいます。これまで貧困を放置してきた社会で、成功してきた社会はないと思います。待ったなしで今やっていただきたい。
持田: 個人も企業も自分ごととして捉えて、そこにあるものなのだと実感して体感して、協力してほしいということですね。
私ではあまり力になれないかもしれませんが、李さんの志を支え、助けになれればと思っています。CESも徐々に日本全国に浸透して、例えば私と李さんの1対1の会話が、もっと大勢での議論になって、世の中を変えるような動きになってほしいと思っています。子どもの貧困問題の解決は李さん一人、LFAという一つの団体だけでは解決できませんよね。だからこそCESのコンセプトに賛同してくれる全国の協力団体と一緒に、地域に根ざした形でたくさんの子どもたちを救っていく、それがどんどん広がっていったらうれしいです。コロナが明けたら、各地を一緒に周って視察し、その後に同じ志を持った地域の人たちと美味しいお酒を分かち合えたら最高だと思います。全国ネットに広げていけるように着実に前に進んでほしいです。そのためのサポート、支援をこれからも行っていきたいです。
Our signature newsletter with insights and analysis from across the firm
By submitting this information, you agree that the information you are providing is subject to Goldman Sachs’ privacy policy and Terms of Use. You consent to receive our newsletter via email.